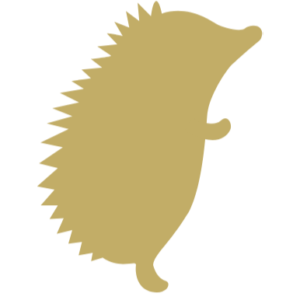作家の「缶詰」というものに初めて触れたのは、サザエさんの漫画だったと思う。
サザエさんのお隣さんであり小説家でもあるイササカ先生が、編集のノリスケさんに見張られながら文机に向かっている――。
場所はイササカ先生の自宅だったか、はたまたどこかの宿であったか。
いずれにせよ大抵の場合、原稿の進捗は芳しくない。
楽しい日常の一ページとは言い難いシチュエーションではあるのだが、当時幼稚園の年長さんであった私は、そのシーンにとてつもなく惹かれた。
たぶん「カンヅメ」の、いかにも狭そうな響きがよかったのだ。
どうにも私は幼い頃から、狭いところに秘密基地を作って籠るのが好きだった。
横倒しにしたコタツ机と壁の間にシーツを張って簡易テントを作ってみたり、押し入れにライトスタンドを持ち込んだり。
そんな狭いところに籠って何をしていたかと言うと、絵本を作っていたのだ。
初めて完成させた絵本のことは、今でもはっきり思い出せる。
森に棲むクマが朝早くからサンドイッチを作って、近所の丘へピクニックに出掛ける、というものだ。
クマの造形と語り口はお気に入りの絵本から着想を得ていた。
言い方を変えれば、かの有名なディック・ブルーナ著、『こぐまのボリス』の二次創作である。
お絵描き帳にクレヨンで描いたそれは、思えば私の初めての同人誌だった。
よくよくすじがきを検めてみれば、現在の私が好んで書いているストーリーの面影が透けて見えなくもない。
私は、未だあの秘密基地とクマの絵本の延長線上にいるのかも――。
となれば、私の缶詰への憧れは、物心つくか否かという時分のめくるめく創作体験に端を発しているとも考えられる。
缶詰への憧れは、かの日の秘密基地への憧れ。
誰にも邪魔をされず、誰の視線に晒されることもなく、自分の作業だけにこどものような無邪気さで没頭できる。そんな特別な場所への憧れだ。
***
私の理想の缶詰環境にも、やはり秘密基地的なところがある。
もし私が缶詰をするとしたら、それこそあの頃の秘密基地のように、ひっそりとした場所を選びたい。
電車の走行音や虫の声は問題ないが、意味のある言葉が――それがどんな言語であれ――耳に入る場所はちょっと遠慮したい。
部屋の明かりは、本当ならライトスタンドを持ち込んで手元だけに絞りたい。
けれど、私もいい大人だ。これ以上視力を落とさないためにも照明はしっかりつけようと思う。
空間はうんと狭いのがいい。
愛用のゲーミングチェアでくるりと方向転換するのが精いっぱいであるくらいの、ちいさな宇宙船のコックピットめいたところに身体を収めて書きたいのだ。
狭い場所の何が素晴らしいかって、手を伸ばすだけであらゆるものを手元に引き寄せられるところだ。
キーボード、紙、万年筆、〇.三ミリのハイテックボールペン黒、辞書、ちょっと落書きをしたいときのための水性ペンと画用紙、ちょっと行き詰まったときに読みたいお気に入りの本、マグカップ、電気ポット、飴玉の包みをいったん放り込んでおくための自立する紙袋――。
ああ缶詰部屋。人生に必要なものがすべて詰まった愛らしき小箱よ!
そんなことを歌い上げておきながら、頭の片隅では冷静な自分がこう言っている。
「それってつまり、今の仕事部屋でしょ?」
そうなのだ。前述したような狭い場所を、私は仕事部屋としてすでに持っている。
便宜上「部屋」と呼んではいるが、どちらかといえば「区画」や「スペース」と表現したほうが実情に近いだろう。
居間の一部を、机と暖簾と食器棚の背面で切り取っただけのシロモノである。
欲を言えば、パソコンのディスプレイがある壁面とドア以外はすべて本棚にしたい。
そもそも居間を区切るのではなく、独立した空間としての部屋がほしい。
電気ポットに水を入れるためだけに部屋を出てキッチンへ向かうのが面倒なので、机の隣にごく小さな冷蔵庫があるといい。その中にはペットボトルに入れた水と紅茶のティーバッグ、そしてちょっとしたクッキーを常備したい。
欲望は尽きない。
しかし今の仕事部屋(あくまで部屋と称する)が完璧になったとして、それで缶詰執筆への憧れまでもが収束してしまうだろうか?
答えは断じて否だ。机をどれだけ大きな本棚で囲っても、個室を用意しても、執筆中に飲んでいる白湯が紅茶に変わっても、私は同じことを言うだろう。
「それはそれとして、缶詰はしたい」
何故そこまでして缶詰がしたいのか。
もしかして、一度缶詰をしてみればわかるだろうか。
そんなことを考えていたら、とある旅館が「文豪缶詰プラン」なる宿泊プランを用意してくれていると知った。
世の中、あるところにはなんでもあるものだ。
この宿泊プランを利用すると、自室旅館のスタッフさんが部屋に食事を運んだり、執筆を見張ったり、編集者のふりをして原稿の催促をしてくれたりする。
まさしく缶詰。しかもノリスケさんまでついてくる。
それなのに――私の缶詰心は、何故かあまり揺れなかった。
「こんなに考え抜かれた丁寧な缶詰なのに? どうして?」
当然ながら、プランのせいではない。
用意されたイベントのバリエーション、設定の作り込み、ホームページの愛らしさ。どれを取っても愛に溢れており、缶詰としてではないなら、ぜひ参加してみたいと思わされる素晴らしいプランだ。
だとしたら、何故――。
たぶん原因は、私の缶詰心が秘密基地と隣り合わせであることにある。
作り込まれた缶詰プランに惹かれなかったのは、きっと、そこに秘密基地的な孤独がないからだ。
秘密基地の中には孤独が満ちている。
けれど孤独な場所に身を置くと、孤独ではないときよりも脳内が騒がしくなる。
具体的には、脳内で延々と言葉を並べ続けるようになるのだ。
目に留まったものすべてに何らかのコメントをしようとすることもあるし、何らかの事柄について、ずっと一人で論じていることもある。
おそらく、いつもは何かを外に出すために使っているエネルギーが、ことごとく内側に向くのだろう。
そんなふうにエネルギーを持て余しながら孤独に言葉を発していると、その言葉に相槌を打つ者の存在に気づく瞬間がある。
相槌の人も、もちろん私の脳内にいる。
たぶんずっといるのだけれど、普段はどうしてか姿が見えないのだ。
次第に言葉を発する人と自分が分離し、言葉の人と相槌の人が二人で会話をするようになる。
そうなればしめたもので、私はその会話をカフェの二席ほど向こうから盗み聞きしながら、とくに気になった部分をこっそり書き留めるのだ。
大抵の場合、そうして書き留めた部分がお話の冒頭、もしくはエンディングのシーンになる。
そのまま二人が勝手に脳内で物語を展開してくれたなら言うことなしだが、これまた大抵の場合、そんなことは起こらないため、私はひいこら言いながらシーンの隙間を埋めていくことになるのだが――。
話が逸れた。しかし、これこそ私が缶詰を欲し、孤独を欲する理由なのだろう。
私の物語は、そも孤独がなければ発生しないのだ。
これでは仕事部屋をいくら理想の缶詰「らしく」したところで、満足できようはずもない。
誰にも気に留められず、心配されることもなく、何日も自分の孤独から発生する事柄だけと向き合ってみたい。――そういう欲求を満たしてくれるのが、私の求める缶詰なのだ。
孤独になりたい。
なんて贅沢な欲求だろうか。
これは孤独ではなくなりたい、と同じくらい贅沢な望みだろう。
しかしどんなに贅沢であれ、これで私の欲する「缶詰」の要件がはっきりした。
狭くて、ある程度静かで、人の声がしない場所。かつ、万が一にも誰かが(荷物の配達の人ですら!)私を訪ねてくることができないであろう場所。
気軽に知人と連絡を取ることができない場所。
そして何より、私を孤独にしてくれる場所――。
そこで思いついた。自宅から少し離れた土地で、安いウィークリーマンションを一週間だけ借りるのはどうだろう?
その期間は仕事の連絡もできれば受けたくない。半年ほど前からきちんと調整して、関係各所に「いついつから一週間、メールが受け取れません」と連絡しておく必要がある。
場所は迷わず京都に決めた。
前々から一度行ってみたいと思っていたのだが、「オフシーズンに行きたい」という金銭的な事情と、「暑い時期と寒い時期には行きたくない」という、盆地出身だからこその本気の我侭が重なった結果、なんとなく機会を逃し続けていたのだ。
幸い、散歩が楽しそうな徒歩圏内に、よさそうなマンションを見つけた。
近くにスーパーマーケットがあり、駅からの距離も申し分ない。
あとは時期を決めるだけだ。そのためにはアレと、コレと、ソレも片付けて――。
そんなことをしているうちに世間はくるっと色を変え、そうやすやすと「自宅から少し離れた土地」を訪ねることはできなくなってしまった。コロナウイルスの影響だ。
計画はとん挫、いや凍結された。だがいつか必ずや本懐を遂げてみせよう。
それはそれとして、缶詰だ。
家の外に出るという手段がひとまずお預けとなった今、缶詰への憧れは膨らむばかりである。
「――とはいえ」ふと、思い至った。
キーを打つ手を止め、目の前のディスプレイをまじまじと見る。
もしかして今、私はすでに缶詰を体験している最中なのではないだろうか?
仕事の連絡手段は以前からメールがほとんどだったが、今や顔合わせも打ち合わせもオンラインで事足りる。
ちょっとした会合や懇親会に誘われることもない。
たとえ誘われたとしてもオンラインだ。
誰とも直接顔を合わせず、ひとりで仕事部屋に籠城し、しばらく会っていない友人たちの近況をSNSで流し見て一人寂しく孤独を噛みしめ――。
「否!」
私の缶詰心が大きな声を上げる。
そんな孤独はお呼びではない。
ならば、どんな孤独ならいいのか。その質問には即答できる。
私の望む孤独は、自ら望んで選び取るものだ。
孤独であることが寂しさを伴ってはいけない。
そんなの他人と会話したくなるじゃないか! 本末転倒だ!
「だから、こんなものが缶詰であっていいはずがない!」
そう叫びながら、私は今日も仕事部屋でキーを叩いている。
いつか京都で敢行する一週間の素晴らしい缶詰生活と、今の仕事部屋にも確かに転がっているはずの「寂しくない孤独」を注意深く探しながら。

























-300x300.png)